腑に落ちるとは行動をすること

フラワーヒーリングセラピストの希依です。
私の話を聞いて腑に落ちましたと感想をいただくことがあります。
とても嬉しいです。
その腑に落ちたこと、その後何か行動に移せているでしょうか。
私は腑に落ちたら行動することまでが言葉の意味ではないかと思っています。
その腑に落ちるは行動することもセットだという理由を探ってみたいと思います。

腑に落ちるとは?
腑(ふ)とは?
まずは『腑』ってなんでしょうね。
腑というのは東洋医学の考え方でお腹のことです。
もう少し詳しくいうと五臓六腑の『腑』です。
五臓は心、肺、肝、腎、脾をいいますが、
六腑は胃、小腸、大腸、膀胱、胆嚢、三焦のことをいいます。
つまり腑は消化器官なのです。
日本でよく使われる言葉には
腹を割って話す
腹をたてる腸(はらわた)が煮えくり返る
腹に一物背に腹は替えられぬ
断腸の思い
腹を据える
日本で昔から例えられてきた言葉には腹が多いですよね。
別にお腹の状態を表しているわけではなくて、
その時の感情だとか本音を表しています。
腹=腸に本音があると見抜いてきたからこそ
こうした言葉が出来上がってきたのですね。
お腹でものを考えている
私たちは『お腹でものを考えている』のです。
このお腹の働きは元々食べたものを消化し、排泄することです。
つまり、学んだことを消化し行動に移す場所だと思うのです。
消化し排泄までできたことは体のためになっているのだから、
行動として現れるはずだと。
腑に落ちたことを行動で示すことが本当に腑に落ちたということではないかと思うのです。
それは本当に心の底に届いている思いませんか?
言葉って面白いですよね。
この考えに至った経緯は
この考えに行き着いたのは上野圭一先生に
なぜ五臓ではなく六腑なのかといえば、
五臓は貯める器官で六腑は消化、排泄の器官だから。
消化し、排泄するほど納得できたと言うことじゃないかな。
そう教えていただいたからです。
上野先生が山本竜隆先生、おのころ理事長と出された本『癒しの心得』の出版記念イベントの際に伺ったことです。
生物学的に見ても
生物学的に進化の順番を見ても
まずは排泄口、腸、口が出来上がってから、
他の体の部位が出来上がってきたのだとか。
それは私たちがお母さんのお腹で受精した時からも
同じような進化を辿ってくるのだそうです。
まずはお腹(腸)から、お腹で考えて進化してきたのがわかっていたから、
腑に落とすという言葉や
腑に落ちない(こちらの方が先に使われてきたようです)という言葉も
腹が立つとかの言葉も生まれてきたのかもしれません。
まとめ
腑に落ちる=消化し行動する
という意味あいも納得いただけたでしょうか。
もちろん、腑に落ちたことがよくわからないけれど、
行動できる人もいますよね。
その人はちゃんと潜在意識で理解できているので、
頭でわかっていないことを始めてしまったのではないかと不安にならずに、
行動していきましょう!








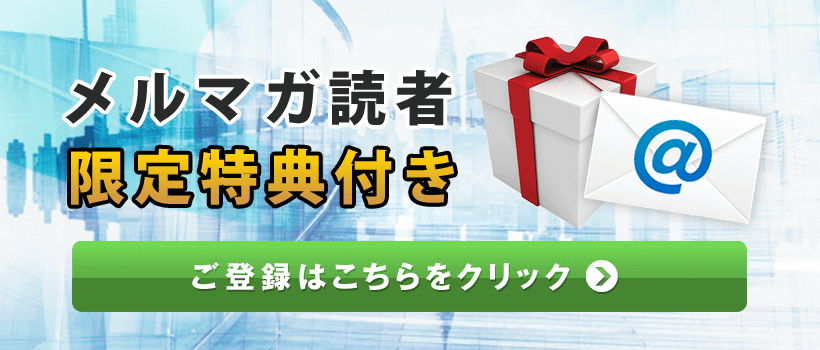

コメントフォーム