香りと薫り、匂いと臭いの違い。読書する時におすすめ〜お香(出来れば沈香)

フラワーヒーリングセラピストの希依です。
この季節、ゆっくりと読書をしたいときに
精油ではなくお香を焚きたくなります。
香りを聞きながらゆったりとした気持ちで読む本は
ちゃんと頭に入ってくるようにおもいます。
昔から日本の香道では
香りを聞く
という表現が使われます。
香りを聞くっていい表現でしょう?
嗅ぐという表現よりも綺麗だし、
嗅ぐというのはいまいちイケてないって感じるんです。
さて香り。 日本には香りの表現がいくつかあります。
香り
薫り
匂い
臭い
違いがわかりますか?
香り
この字は「黍(きび)+甘(うまい)」というきびを煮た時のいい香りが元になっています。
いい香りの香水や香料に使われます。
アロマテラピーではこれが一番しっくり来るように思います。
薫り
この文字は「草をくゆらす」という意味があります。
植物のそのものの香りが立ちこめている感じです。
いぶしたりするみたいな。
お香でも「薫香」と言います。
この薫という字は草を燻すということから出来た文字なのそうです。
また抽象的な風の薫りとか初夏の薫りなどの表現も使われています。
臭い
この字を見てどんな臭いを想像しますか?
なんとなく嫌だなあと思いますよね。
ま、そういう時に使います。
匂い
それ以外ですね。
いい匂いという言葉遣いは芳香が素晴らしい時にも使います。
この「臭い」「匂い」という2つに関しては、
「嗅ぐ」と続きます。
いい匂いでもあまり良くない臭いでも「かぐ」でした。
でも「香り」と「薫り」には、「聞く」と続けてきたのです。
お香の薫り。
これは常にそばにあっていいと感じる心地よい香りのこと。
それは五感で感じる香りを愉しむこと。
静かな中に、香木から立ち上る香り、
この香りは一体なんだろう?と脳が覚醒していく感覚。
香木の声を聞いているようなもの。
日本語の表現は多彩ですね!

鼻の奥の神経と脳が直結しているので、
(鼻の奥に脳がむき出しになっているイメージ)
香りはダイレクトに脳に届きます。
だからこそ心理的に揺さぶられることがあるのだと思います。
それは素敵な思い出とともに呼びさまれる感情だったり、
大好きな香りと認識してうきうきしたり、
心地よい香りの中で意識することも含めて「聞く」のです。
香りの奥深さを感じますね!
日本の香りのことを言えば、
香道では沈香の香りの違いを楽しんでいたのですから、
ホント優雅なものです。 (香道ではめったに白檀を使わないそう)
今や、楽しむ香りは数えきれないほどありますね。
植物の数だけ精油はあると考えると気が遠くなります。
もっとも製品になっているのはわずかな数ですけど。
匂いは嗅ぐけど、香りは聞く。
言葉の多彩さと表現の豊かさも楽しみたくなって
秋はお香を焚きたくなるのです。
本を読み無ときにお香が焚きたくなったら
ぜひ沈香を。







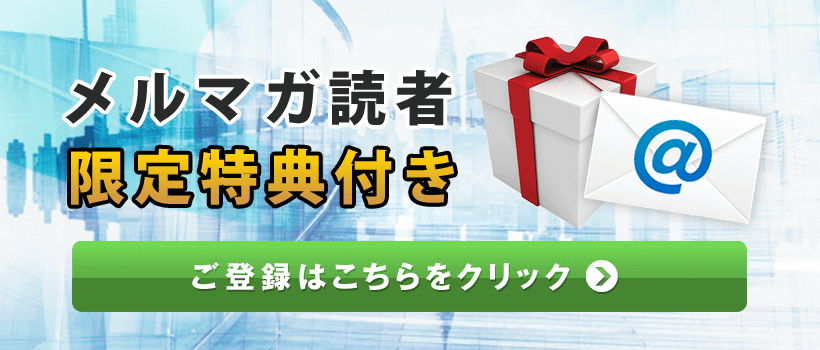

コメントフォーム