古より灰にも霊力があったらしくお神酒に使われた〜クサギ

フラワーヒーリングセラピストの希依です。
新嘗祭は毎年天皇陛下が行う宮中祭祀ですが、
その宮中祭祀と神社の祭礼の際に神様に供されるお神酒(おみき)があります。
それが『白酒(しろき)』『黒酒(くろき)』というものです。
先日、その白酒と黒酒をセットでいただきました。ありがとうございます。
白酒はその年に収穫された新米から作られた白濁したお酒で、
黒酒はその白酒にクサギ という木を蒸し焼きにして炭化した灰を加えたものです。
元々は古代米の黒米を使って作っていたものだったようですが、
黒米が廃れていき、クサギの灰がつかわれるようになったとか。
クサギには何かしらの神聖な力があると考えられていたと考えられますが、
何故なのかはわかりません。
現在も宮中祭祀のために昔ながらの製法で作られているそうです。

万葉集には
天地(あめつち)と 久しきまでに 万代(よろず)よに
つかへまつらむ くろきしろきを
と詠まれています。
クサギ はクマツヅラ科の落葉樹で、葉に特殊な香りがあります。
だから和名も臭木と言います。
漢名も臭梧桐(しゅうごりゅう)といい、臭いというところからきています。
日本全国、北海道から沖縄まで自生し、藪や林などの半日陰を好みます。
このクサギの葉の臭いは茹でたり蒸したりすることによって無くなるので、
各地方では色々な料理に利用されてきています。
古くから茹でた若葉をざるに広げて天日でよく乾燥させてから保存、必要な場合に水で戻して汁の実などにも用いられていました。
春に出る若葉でのおひたしなどの料理に、お寺での精進料理には良く見られるとか。
岡山の北部にはクサギナ飯という伝統料理があります。
ゆでた後乾燥保存した葉を水で戻し、こぼうや人参とともに醤油、酒、砂糖などで含め煮にします。
別鍋で山鳥の肉を醤油、酒などで味付けした汁を作り、できた含め煮をご飯に乗せて汁をかけていただくというもの。
宮崎県椎葉村にもこのレシピとほぼ同じレシピの郷土料理があります。
これは椎葉村が平家の落人村で、岡山に住んでいた平家一門の人が持ち込んだのではないかと言われています。
夏7~8月に白い花を枝の先にまとまって咲かせます。
秋に熟す果実は青黒く光沢があり、果実の周りの赤く星形のガクとのコントラストが美しいです。
この果実は煮出した後媒染なしでとても美しい緑がかった青色に染め上がります。
赤いガクは鉄媒染で渋い黒に染め上がります。
ちなみに、私がいただいた黒酒はクサギの灰ではなく竹炭が使われています。
お正月のお神酒にさせていただきたいと思います。







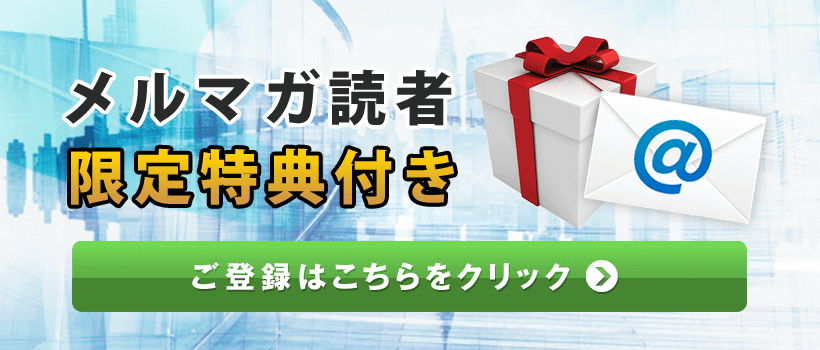

コメントフォーム