生田緑地で秋の花、萩を楽しむ

フラワーヒーリングセラピストの希依です。
植物観察会へ行ってきました。 場所は初めての生田緑地。
本当に広いんですね〜 びっくりしました。
植生も豊かで気持ちが良かったです。
今回はマメ科などの植物を多くみてきました。
花が咲き、実がなる頃に植物の特定がしやすくなるのだとか。
確かにあの葉っぱにツルじゃ確かにわかりにくいですね。
私、秋の七草でハギがどうしても区別がつかなかったんです。
今回で4種類も区別がつきました!
ハギの花は日本を代表する秋の花で、マメ科ハギ属の落葉低木です。
万葉集にも詠まれており、古くから親しんできた花で、
さかんむりに秋と書いて『萩』という和名になったとか。
日本人の先人の感性はすごいなと思います。
また花が終わった頃の根を掘り出して水洗いして、細かく刻んで乾燥させたものを
婦人病ののぼせやめまいなどに使っていました。
水戸光圀が藩の医師、穂積甫庵に命じて作らせた『救民妙薬』という書物に
この萩の花の記載があるのだそう。
この救民妙薬は庶民のために野山の草木、動物など手に入るものを利用して薬を作ることや
日常の健康法などをまとめたもので、解りやすい言葉で書かれているのだとか。
AmazonにあったのでDLしたのですが、昔の文字を判読するのも難しい笑
ヤマハギ
うーん、微妙にピンボケ

ミヤギノハギ(すだれのようになって咲く)

ヌスビトハギ(在来種)
いつの間にか洋服に種がくっついて運ばれていきます。

アレチヌスビトハギ(外来種)

区別がとても細かいけれど、 少しづつ形は違っているのね。
ハギのお花がとても好きになった1日でした。
他のお花はおいおい書きます。
*メルマガ登録でもお花や心や体のことなどを発信中!
登録してね!
https://kie-aroma.jp/p/r/lTr4YC8P







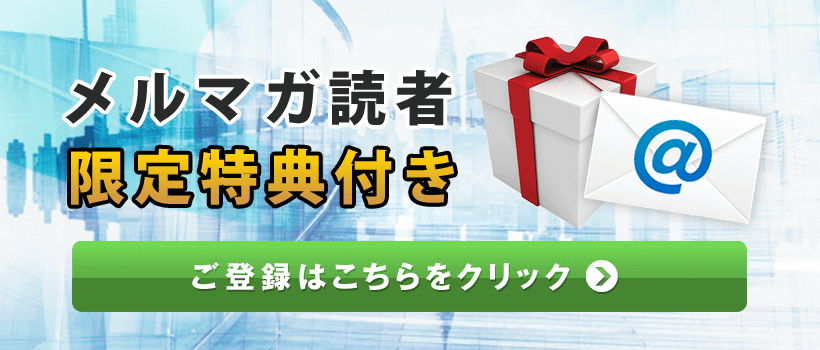

コメントフォーム