地域性が見える調味料〜七味唐辛子

フラワーヒーリングセラピストの希依です。
資料整理をしていたら、
七味唐辛子を手作りした時の資料が出てきました。
これは講座でオリジナル七味を作った時のもの。
そういえばこうやって作ったなあなんて思いつつ、七味唐辛子のお話を少し。
七味唐辛子が初お目見えしたのは1625年。
江戸時代の3代将軍の家光時代です。
からしや中島徳右衛門が両国の薬研堀(やげんぼり)にて、
漢方薬をベースに食事に利用するために考案したものです。
この薬研堀というところには薬問屋や医師が多く集まっていました。
医者町とも呼ばれていたこの地域の堀の形が薬研という薬をひいて粉末にする道具の形に似ていたことから
日本橋薬研掘町と言ったそうです。現在の東日本橋1丁目のあたりだそう。
だから七味唐辛子のことを薬研堀(やげんぼり)ともいうのですね。

ちなみに七味(しちみ)というのは関西風の呼び方で、
関東では七色唐辛子とか七種唐辛子(なないろとうがらし)で、
「なないろ」とか「なないろとんがらし」と呼んでいたのだとか。
そして輸出する際には「NANAMI TOUGARASI、ななみとうがらし」
一味と七味が間違えやすいからだそう。
やげん堀さんの七味の中身は
赤唐辛子(乾燥、焙煎の2種類)、山椒、陳皮、黒胡麻、麻の実、芥子の実
江戸の庶民に好まれた蕎麦の薬味として、
関東では濃口醤油に蕎麦で広まっていったのですね。
関西では薄口醤油にうどんがメインで風味を大事にすることから、
青海苔や白胡麻、青紫蘇が入っています。(京都の七味屋本舗さん)
また長野では関東よりも醤油の味も辛く味が濃いことから、
辛口醤油に蕎麦の薬味として、生姜や青紫蘇が入り赤唐辛子の量も多いのだとか。(八幡屋礒五郎さん)
食べるものによってその七味の風味が違うのですね。
七味唐辛子も使い分けてみたくなりますね。
あなたのおうちの七味唐辛子はどんな七味唐辛子ですか?







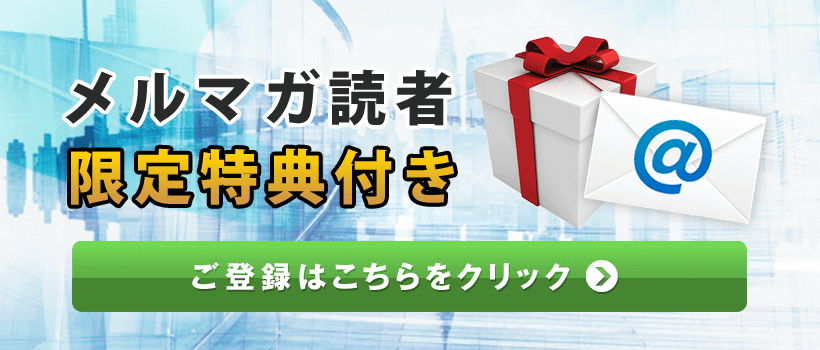

コメントフォーム