神様も富士山の寒さでお腹を壊す?〜治した植物のお話

フラワーヒーリングセラピストの希依です。
今日はマニアックなお話です。
植物民俗学のレポートを1つ書くために資料を集めているのですが。
植物の一番古い日本の記述と言えば記紀なわけですよ。
古事記と日本書紀が現存する一番古い記述なので
そこに出てくるのが一番古いということになります。
ということで
内服薬はタチバナ
外用薬はガマの穂
が最古の植物治療の記述になっているということです。

今回私が調べている植物がなんとホツマツタヱに記述がありました。
ホツマツタヱはご存知でしょうか?
オシテ文字と呼ばれる神代文字を使って書かれた古史古伝のひとつとされ
記紀の元になったとされる一方で、偽書とも言われているものです。
このホツマツタヱが本物か偽書かどうかは別にしても、
ちゃんと植物に関しての記述があることにワクワクです。
内容は
天照大神の孫の瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)が天孫降臨され、
富士山周囲の巡視された際に、体が冷え腹痛を起こされ、
はぐは、千代見草、ひとみ草の三草を煎じたものを服用され癒されたというもの。
瓊瓊杵尊も天孫降臨して富士山の寒さでお腹を壊したんですねw
もっとも記紀には富士山の記述がないので、このエピソードは出てこないわけです。
今も昔もあの富士山の素晴らしさは変わらないと思うのですが、
なぜ記紀には出てこないのでしょうね?
まあそれは置いておいて。

このはぐはは桑のこと、千代見草はヨモギのこと、ひとみ草は人参のことだとされています。
桑とヨモギと人参のお茶。確かにお腹に効きそうです。
たくさんある薬草の中ではぐは(桑)は老いた身も若返らせる薬草として、
桑の葉で養蚕が始まったと伝えられているとのこと。
植物の歴史を調べていると面白いところにたどり着いたりしてそれはそれでワクワクです。
縄文時代から日本人と暮らしてきた植物が垣間見えてとても面白いですね。
私はホツマツタヱが偽書ではないと思いたいです。







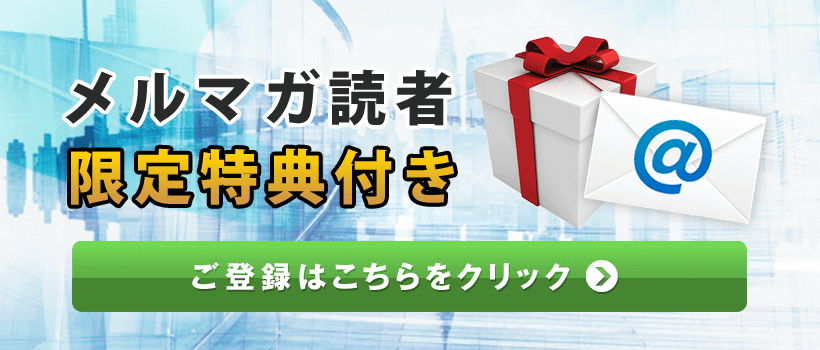

コメントフォーム