桃の節供の植物たち〜橘と桃

フラワーヒーリングセラピストの希依です。
今日は令和3年3月3日。
3が3つも重なる素敵な日です。
そして今日は上巳の節供、桃の節供とか雛祭りと言われる厄払いの日です。
上巳というのは3月最初の巳の日のことです。
この頃は季節の変わり目で、
古代中国では禍をもたらす邪気が入りやすいことから水で穢れを祓う習慣がありました。
それが日本に伝わり宮中祭祀に取り入れられ禊の神事と結びつきました。
そして草や紙で作った人形で自分の体を撫でて穢れを移し、
川や海へ流したりするようになりました。これが流し雛です。
そして流すだけではなく飾るようになり雛人形が誕生したわけですね。
このお雛様の飾りの中に桜の木と橘の木があります。
桜は雛人形に向かって右、橘は向かって左側に飾るのが一般的。
『左近の桜、右近の橘』とも言われます。
私たちは雛人形に向かって飾りますが、桜と橘の位置はお内裏さま、お雛さまから見た左右になります。
橘は京都御所でもそのように植えられていることに由来するそう。
橘は日本唯一の野生種柑橘類です。

香りの強い果実は太陽に向かって生え長く木に残ります。
古事記にも書かれている不老不死の妙薬である
『非時香菓(ときのじくのかくのこのみ)』は橘ではないかとされています。
葉には痴呆予防や改善に効果のある成分があることがわかったのだとか。
とても小さな実ですが、やっぱり不老不死の妙薬なのかもしれません。
桃は穢れを払う神聖な木とされていました。

桃の節供に使われる桃の花は果実を作らない桃(ハナモモ)です。
花柄が短いので枝にびっしり花がそのまま付いているように見えます。
残念ながら桃の花には香りはありません。
伊奘諾尊が冥界の伊弉冉尊から逃げ帰って来るときに追手を払うために投げたものが桃だとされていますよね。
節分の豆まきは本当は桃を使いたかったとのことですが、
季節的にないので豆で代用したという話も聞いた事があります。
桃で節分の厄払いはちょっと想像できないですね笑







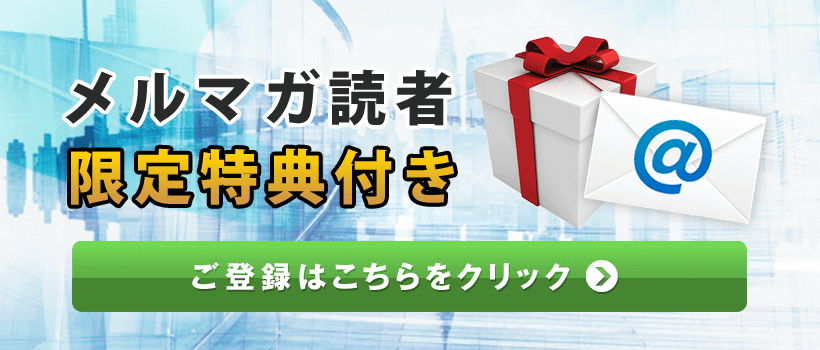

コメントフォーム