クワについて調べていたら『ホツマツタエ』に行き着いた

フラワーヒーリングセラピストの希依です。
植物民俗学(和ハーブフォークロア)の書籍紹介2冊目。
私がテーマにしたのがクワということもあって、
クワの記述を求めて探し回って見つけた書籍が『ホツマツタエ』で、
今回私が購入したのは今村聡夫氏の『はじめてのホツマツタエ』
記述があったのはその地の巻でした。
ホツマツタエは知っていたものの植物の記述まであるとは正直思っていなかったです。

ホツマツタエは古代大和言葉(オシテ文字)で綴られ、
正式な日本の歴史書としては偽書扱いされているものです。
全編が五七調の長歌で綴られ、40章(アヤ)、10,700行で構成されています。
古事記よりも古いかどうかは分かりませんが、
古事記とは違った視点で当時のことが書かれていると考えるなら
とても面白いものだと思っています。
さてそのホツマツタエと古事記の話は置いておいて、
クワの記述があったのは『はじめてのホツマツタエ』の地の巻でした。
私が手に入れた書籍によれば、4つほどの記述を確認できました。
ハラミ山(富士山)に登ったニニキネは火口湖をコノシロ池と名付け、その池にいた都鳥(大型の千 鳥)にラの花(クワの花)を投げているところをコモリのミホヒコが周辺に生い茂っていたハ(ヨモギ)の汁でニニキネの御衣装(ミハモ) に千鳥とラの花を描いた。ニニキネはその後政を行う際に、その御衣装を召されたとのこと。 このハの汁で染めた布は青みがかった黄色でその色を山鳩色という。
ラははぐは(葉桑)、艾(もぐさ)、蕪ろ葉などは『血を増して老いも若やぐ効能』として人の健康を増進させる神性を宿している。人の 健康と若さを宿した神をワカムスヒというがその神を宿しているとされた。
ワカムスヒの神性は蚕にも宿るとされ、その蚕が吐く糸はシラヤマ姫(菊理媛、くくり姫)によって御衣(ミハ)として織られ、甥の天照 大神(ホツマツタエでは男神)誕生の際に奉られたとされている。シラヤマ姫のお住まいの白山地方は扶桑寝の邦(コエネノクニ)と 名付けられた。
富士山のハラミ山の由来は、ハ(ヨモギ)ラ(クワ)ミ(人参)の薬効に優れた草が繁る山ということから名付けられたらしい。
この本が書かれた当時からクワがたいせつな植物だったことが伺えますね。
もう少し読み込むとまだまだ植物が出てきそうなので、楽しみに読んでいこうと思います。







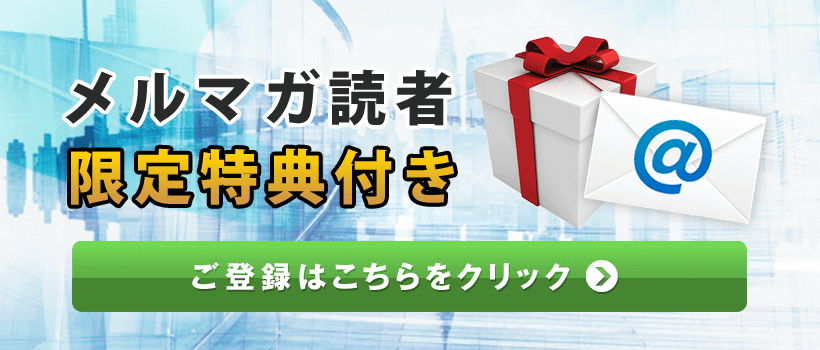

コメントフォーム